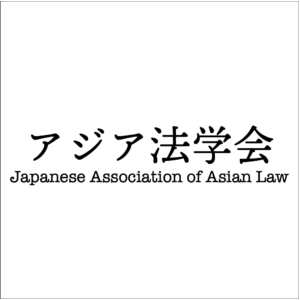2025年度アジア法学会研究大会
アジア法学会 会員各位
2025年度アジア法学会研究大会について、以下の通りご案内いたします。
1.シンポジウムのタイムテーブルと報告タイトル
【開催日】2025年6月22日(日)
【シンポジウムのテーマ】「アジアにおける宗教と法の現状」
【場所】明治大学駿河台校舎グローバルフロント1階多目的室
【タイムテーブル】
10:00-11:00 基調報告 「宗教的なるもの」と「制度としての宗教」――『異議申し立て』を受けつつ形成されるものの批判的考察をめざして――(孝忠延夫)
11:15-11:45 報告「インドにおける宗教にかかわる司法判断」(浅野宜之)
11:50-12:20 報告「インドにおける法と宗教の絡み合い―あるヒンドゥー寺院をめぐる紛争と法宗教学という視点―」(田中鉄也)
12:20-13:30 昼休み・理事会
13:30-14:00 会員総会
14:05-14:35 報告「タイ仏教僧侶への民衆の期待と法のあり方―財産取得に関するタイにおける議論状況を通じて」(西澤希久男)
14:40-15:10 報告「選挙権威主義体制における国教の役割:カンボジアの場合」(傘谷祐之)
15:10-15:20 休憩
15:20-15:50 報告「インドネシアにおけるイスラーム法」(島田 弦)
15:55-16:25 報告「ムスリム諸国における宗教規制ー法多元主義に着目して」(桑原尚子)
16:25-16:35 休憩・質問等とりまとめ
16:35-17:35 総合質疑
17:40 閉会の辞
18:00 懇親会
2.研究大会(午前、会員総会、午後)及び懇親会への出欠登録
研究大会及び懇親会の出欠についてお伺いいたします。
研究大会及び懇親会の出欠登録について、下記のGoogle Formよりご回答ください。
懇親会費は5,000円程度を予定しています。
当日にお支払いをお願いいたします。
出欠登録は、2025年6月16日(月)までにお願いいたします。
多くの会員の皆様のご参加をお待ち申し上げます。
なお、各報告の要旨を含めた研究大会のプログラムについては、改めてご案内いたします。
アジア法学会事務局
アジア法学会2025年度研究大会 シンポジウム「アジアにおける宗教と法」
企画趣旨
これまでアジア各国なかでも南アジアや東南アジア地域においては、宗教と法との関係について議論する際に、法制度へのさまざまな影響に焦点を当てる例が多く見られた。南アジア地域を例にとればインドにおける家族法分野への宗教法の影響、あるいはパキスタンなどにみられるシャリーアなどが挙げられる。そうした法制度面での検討も当然求められるところであるが、同時に政治、社会生活、法との相互関連における宗教の影響を動態的に検討することも求められる。本企画においては、特に主要な宗教とされるイスラーム、仏教、ヒンドゥーに焦点を当てて、これらの宗教が各報告者の専門とする諸国(地域)において、法に対していかなる影響を及ぼしているのか、あるいは法制度の整備にあたって宗教についていかに対応し、ときに取り込もうとしていたのか等、宗教と法との関係性について動態的な検討を含めて示していただき、そのうえで宗教と法について検討する足がかりとする。
なお、各宗教に関わる報告に先立ち、孝忠延夫会員による基調報告をもとに、宗教と法について検討するに当たっての俯瞰図を示していただく予定である。
【基調報告】
孝忠延夫(関西大学名誉教授)「「宗教的なるもの」と「制度としての宗教」 ――『異議申し立て』を受けつつ形成されるものの批判的考察をめざして――」
はじめに一 これまでの(研究の)歩みをふりかえる
序 「アジア法学会」および拙稿一覧
1 「政教分離」の憲法的性質について――憲法・判例の「解釈論」として
2 「信教の自由」の成立史とその内容
3 「セキュラリズム」とは?
4 「国民・国家」形成と「国民統合」を「信教の自由・政教分離」から考える
二 「異義申し立て」としての宗教と「制度としての宗教」
1 「異義申し立て」としての宗教
2 「制度としての宗教」
3 方法論について
三 「アジア法研究」と「宗教」
むすびにかえて
【報告;ヒンドゥー】
浅野宜之(関西大学)「インドにおける宗教に関わる司法判断」
近年、インドにおいては宗教に関わる訴訟が様々に提起され、その内容が広く報道される状況がみられる。本報告では、そのうちもっとも有名な訴訟である「アヨーディヤー判決」(バーブリー・マスジッド判決)について概要を紹介したのち、現在最高裁判所に係属中である「1991年礼拝所法(Place of Worship Act, 1991)」の違憲性を問う訴訟、および「2025年ワクフ改正法(Waqf (Amendment) Act, 2025)」の違憲性を問う訴訟について取り上げ、現代インドにおけるそれらの司法判断の意味について考察する。なお、後二件については本稿執筆段階で未だ裁判所の判断が示されていないため、本シンポジウム実施時点においては概観した上で今後の展開を検討するに留まる可能性は否定できない。
アヨーディヤー判決は、2019年11月に最高裁において下された判決である。本件は、ウッタル・プラデーシュ州アヨーディヤーの地に建立されていたバーブリー・マスジッドに対し、ヒンドゥーの一部宗派の信者が当該モスクのある場所をラーマ神の生誕地として崇拝し、これが高じて同モスクの破壊にいたったことを契機として注目を集めた事件に関わるものである。本報告では当該訴訟の概要と論点のうち神格の問題と憲法の理念の問題について取り上げる。
「1947 年礼拝所法」は近年インドにおいて法的議論がなされている法令のひとつである。この法律は当初、1947年8月15日に存在していた礼拝所の「宗教的性格」を保存し、転用を防止するために導入された。しかし、最高裁には、その合憲性に異議を唱える複数の訴訟が提起されている。その訴訟とは、この法律が憲法上の「信教の自由」や「セキュラリズム」に違反していると主張するもので、逆に宗教対立を招かないためにも同法の厳格な施行を求める訴訟も提起されているところである。本報告では同法に関わる訴訟について概観し、同法に対する司法の対応を検討する。
2025 年ワクフ改正法はモディ政権主導で制定された改正法である。ワクフとは、金銭的利益を生み出す固定資産を寄付する、慈善活動をいう。ムスリムは教育、墓地、モスクの建設などのためにワクフを寄付するものとされている。ワクフの運営に関する法律であるワクフ法は 1954 年に制定されていたが、「ワクフの運営に透明性をもたらせるため」改正がなされたものである。しかし、この法律に対して違憲性を問う訴訟が提起されている。これについては最高裁に係属中であるため、概要を示すにとどめる。
以上の検討を通じ、現在のインドにおける政治背景のなかで、司法が宗教問題に対していかなる姿勢をもっているのかについて展望する契機とする。
田中鉄也(中京大学)「インドにおける法と宗教の絡み合い―あるヒンドゥー寺院をめぐる紛争と法宗教学という視点―」
本発表は、これまで発表者が現地調査を行ってきたラージャスターン州のラーニー・サティー寺院(以下、R寺院)を事例に、インドにおける法と宗教との絡み合いの特徴を考察するものである。この寺院は中世期にサティーと呼ばれる寡婦殉死を経て神格化した女神を本尊に据えているために、1987 年の寡婦殉死事件を契機に、規制の対象となってきた。他方で、「サティー(犯罪)防止法」( 1988年施行)に基づけば閉鎖せざるを得ないのだが、この寺院は今でも盛況に運営されている。R寺院を分析することを通じて、インドにおいて法と宗教とがお互いに与えあう相互規定的な影響のあり様を検証したい。
【報告;仏教】
西澤希久男(関西大学)「タイ仏教僧侶への民衆の期待と法のあり方―財産取得に関するタイにおける議論状況を通じて」
本報告では、民商法典に定められている、仏教僧侶のみに適用される条文に焦点をあて、経済活動が禁止されているにもかかわらず、出家中または還俗の際に財産取得を可能とする現行制度に対する議論状況を通じて、タイにおける仏教と法の関係について検討する。
傘谷祐之(名古屋大学)「選挙権威主義体制における国教の役割:カンボジアの場合」
カンボジア1993年憲法は、政治体制として「複数政党制の自由民主主義体制」(前文、第1 条、第51条等)を採用したが、近年、与党・人民党は選挙権威主義への傾斜を強めている。その状況下で、国教である仏教(第43条)が人民党に対する人々の支持をいかに調達しているか、公式・非公式の法制度の検討を通じて明らかにする。
【報告;イスラーム】
島田 弦(名古屋大学)「インドネシアにおける宗教法:宗教規範の国家管理」
本報告は、インドネシアにおける宗教法、宗教規範と国との関係を、国が宗教規範を管理するという視点から検討する。 インドネシアは人口の90%以上をムスリムが占めるが、イスラームを国教とはしていない。国是とされるパンチャシラ(五原則)は、インドネシア共和国は「唯一絶対神への信仰に基づく」として、インドネシアは特定の宗教国家ではないが、非宗教国家でもないとする原則を採用している。 この原則の下で、国は「宗教」を定義し管理してきた。つまり国が「宗教」とその教義を公認し、「宗教」に法的地位を認めるが、同時に宗教と宗教法を管理する法制度となっている。それは、同時に「宗教」でない「信仰」を否定するか、「信仰」は「宗教」の下位類型と見做すことを意味する。
このような国と宗教の法的関係は、スハルト権威主義体制の社会統制政策の一環として強化されたが、オランダ植民地政策にもルーツがあり、また、1998年の民主化以降も存続している。本報告は、宗教侮辱法、婚姻法、住民行政法、宗教裁判所法などの法律とそれに関する憲法裁判所判決を利用して、インドネシアにおける国と宗教の法的関係を考察する。
桑原尚子(岩手県立大学)「ムスリム諸国における宗教規制ー法多元主義に着目して」
イスラム教徒が多数派を占める国々(以下、ムスリム諸国)の多くでは、いわゆる国家主導の法多元主義(legal pluralism)を認めている。法多元主義の制度的構造、法領域の範囲及び法的効果には違いが存するものの、それは、国家という政治共同体の成員であると同時に宗教共同体に帰属していると自らを認識し、複数の「法」的権威に従う人々に対処するための統治技術ないし法的包摂と排除のメカニズムといえる。現在のアジア、中東やアフリカの諸国における法多元主義は植民地法制の遺制であるとともに、近代西洋起源の「国民国家」という概念枠組みの下で、宗教や民族の異なる人々をどのように統治するかという問題に対応する法政策の側面を有する。
西洋近代法は、理念的には、多様な宗教的及び民族的背景を持つ人々の統治にあたり、「市民」概念、世俗主義、中立性、法の普遍性/法の一元化と法の下の平等を制度的基盤としてきた。西洋近代法における「市民」概念は、個人が宗教的帰属から自律した、法の下で平等な存在であることを前提する。これに対して、多くのムスリムにとって宗教的アイデンティティは私事としての信仰にとどまらず、社会的実践とシャリーアの遵守が一体となって機能しており、宗教法に従うことは自己の尊厳や正義と深く結びついている。そのため、「市民」として宗教的に中立な国家法に従うことと、ムスリムとして宗教法に従うことがときに緊張を孕む。法多元主義はこの緊張を緩和する役割を果たしうる。他方で、国家主導の法多元主義が本質的にヒエラルヒーを内包し宗教法を国家法の下位に固定化する(Merry 1988)、イスラーム法の制度化を通じて女性や宗教的少数派といった「弱者」にとって不利益な制度として機能しうる(Mir-Hosseini 1999, 2003; An-Na’im 2008)といった、法多元主義が有する制度的限界や社会的な権力関係の構造化への批判的検討の必要も指摘されている。法政策という観点からすると、問題の中核は、宗教的権威を制度的にどう扱うか、多元的な「法の正統性」をどのように法制度に組み込むかである。
本報告では、ムスリム諸国における宗教的権威の制度的位置付けと多元的な「法の正統性」の制度化を比較法的に分析することで、国家による宗教規制の構造的特徴と政治的含意を明らかにする。これは、ムスリム諸国における宗教と国家の関係を「世俗か宗教か」という二分法ではなく、宗教的権威と国家権威がどのように混ざり合い、制度化され、操作されているのかという観点から動態的に捉える試みでもある。